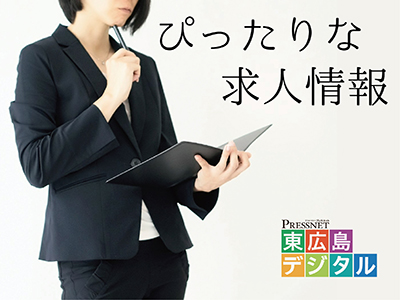プラスチック成形のエキスパートといっても過言ではないだろう。会社員時代には、30件にも及ぶ企業特許の取得に尽力。県の技能検定委員を35年間務め、後進の育成にもあたってきた。こうした取り組みが認められての瑞宝単光章受章に「名誉なことでうれしい限り」と目を細める。(日川)
生まれ育った環境が、モノづくりに興味を抱くきっかけになった。実家(高屋町)の周囲に広がるのは山と田んぼだけ。「子ども心に何かをしようと思ったら、自分で遊び道具を作るしかなかった」と、豆鉄砲や竹とんぼなど、思いつくままに工作に夢中になった。
高校卒業後は、勤務した会社で、プラスチックの原料となる樹脂の基礎研究や、プラスチック成形の開発に従事。ペットボトルやファスナー、食品トレー、自動車部品などの開発を次々と手掛け、特許を取得していった。ちょうど日本の高度経済成長期とバブル経済期と重なり、「日本の経済発展のためになるという一心で、がむしゃらに働いていた」。磨いてきた加工技術のスキルは、特級の技能士資格の取得に結び付き、県の技能検定委員に推挙されるほどになった。
一方で、大量生産、大量消費の時代は、大量廃棄や二酸化炭素排出に伴う地球温暖化の問題をもたらし、環境に大きな影響を与えてきた。「消費者の立場で、私でもできる環境にやさしい取り組み」を模索し、たどり着いたのが不要になった日用品を使った手作りの楽器演奏だった。
20年前からバケツやじょうろ、イスなど身近にあるプラスチック用品で笛を手作り。学校や老人福祉施設などでボランティアの演奏を続け、トークを交えながら大量消費の弊害などを訴えてきた。手掛けた笛は40種にも及び、『何でも笛にする面白おじさん』として何度もテレビに取り上げられた。「子どもの頃は、音楽といえばスズメとカラスの鳴き声しか聞いたことがなかった私が、まさか音楽をするなんてね(笑)。だから人生は面白い」。コンサートでは、こんなユーモアセンスに満ちたトークで、子どもやお年寄りと心を通わせてきた。
今回の受章を「なんでもやってみたい性格が奏功したのかな」と相好を崩しながら、「たとえ中途半端と言われようと、これからもいろいろなことに挑戦したい」。この人らしい言葉で締めくくった。
米川さん手作りの楽器