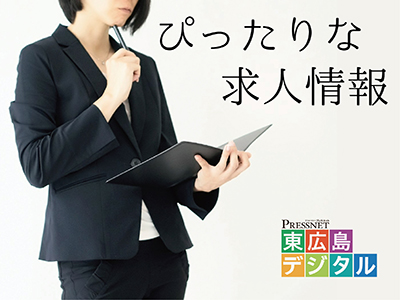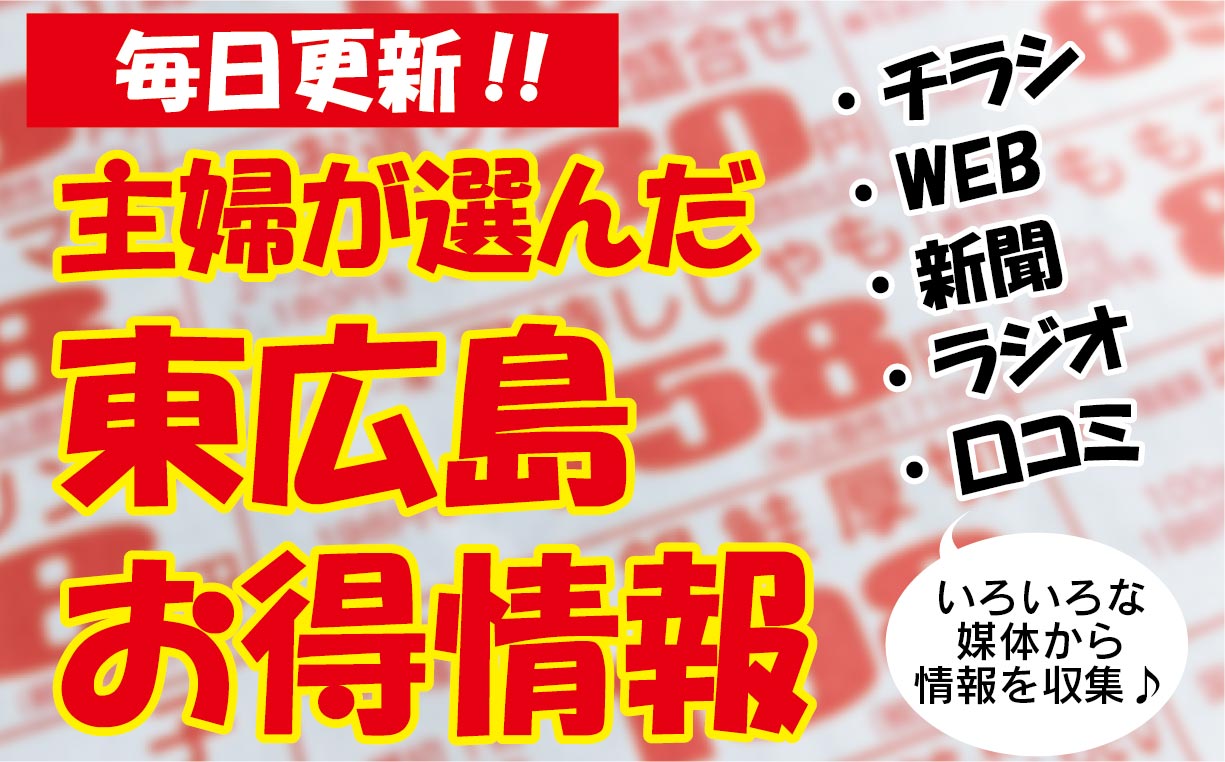広島大発のベンチャー企業として、遺伝子を改変するゲノム編集の研究成果を企業と組んで製品開発や事業化まで展開していくことが目的だ。「新たな価値を創造するスタートアップは、さまざまな可能性を秘めている。広島のユニコーン企業になれるよう、成長を続けていきたい」と力を込める。(日川)
もともとは研究者になるのが夢だった。広島大総合科学部に入学後、バイオ分野の学者になることを目標に同大学院の博士課程まで進んだ。ただ、当時は博士号取得後に、任期制の大学の研究職に就く、いわゆるポストドクターが多く、「研究者があふれ、研究者で食べていくことに不安を感じていた」と振り返る。
そんなとき出合ったのがJST(科学技術振興機構)。企業と大学が連携したプロジェクトを全国から公募し、採択したプロジェクトに資金を提供するという、「研究を支援する」仕事に就いた。その後、内閣官房に出向、国の知財戦略策定に携わった。20代後半で積んだキャリアは、大きな財産になった、という。
転機になったのは、東広島市職員となり、産学官連携を促進する広島大に出向し、日本のゲノム編集研究のトップランナーだった山本卓教授と出会ったことだ。JSTの経歴を買われ、山本教授の研究をテーマに、JSTのプロジェクトに提案、採択されたのを機に市役所を退職。2019年、山本教授と一緒に、プラチナバイオ社を立ち上げた。
プラチナバイオ社は、企業とともにゲノム編集技術を使った製品の開発する「共創」、ゲノム編集を使う企業に安全性などのコンサルティングサービスを行う「社会実装」、ゲノム編集のデータ基盤を開発する「バイオ×デジタル」を事業の柱に据える。
これまでに、プロジェクトの成果として、卵アレルギーの人でも安心して食べられる「低アレルゲン卵」や、二酸化炭素を吸収する微生物を利用してつくるバイオ燃料などを開発した。「会社の真価が問われるのはこれから。生産規模を拡大し、事業化につなげたい」と話す。
現在のスタッフは19人。経営企画、事業推進、研究開発の3部体制で、研究開発以外のメンバーは、フルリモートが会社のスタンスだ。「会社の生命線は人材。日本全国どこからでも参加できる利点を生かし、多様な分野で仲間を集めたい」と目を輝かせる。